諸事情で憤慨することがありまして、その恨みを肉体で返すと刃傷沙汰になるものですから、やはりここは歌で勝負ということで、奮闘したことを書きます。
まず歌詞が降りてきました。数々の立腹、憤慨、悲哀、そんなものがいくつも現れて僕の前に立ちふさがります。それをまずはLINEに書き留め、同じ思いの友人に見せたところ、非常に的を得ているという返事でしたので、これらを用いて曲を作ることにしました。
カタルシス
歌詞をまとめます。誰が主人公なのかを決めます。僕の場合は本人と第三者が物語の中心になることが多いです。そんな感じで自分がいかに卑怯者か、身勝手かを、リスナーの方が同情できるような口ぶりでまとめます。出せるだけのネタを色々と書き留め続けます。歌の中の世界ですから容赦はしません。いかに虐げられたのか、いかに逆襲できたのか、最後にはそれまでの鬱憤を晴らせるような心情で終わらせます。そうすることでリスナーの方はスーッとするわけです。これをカタルシスといいます。
サビの作曲
この曲は2番までと決めていたので、2番も同じように憤慨した内容を「1番とほぼ同じ文字数」で書きます。ここがポイントで、僕は「いとしのエリー状態」と呼んでいるのですが、1番と2番の文字数が違っても曲は成立するという意味で使ってます。ただ極力それは避けたいので、ほぼ同じになるよう調整します。ガラッと書き直すこともあります。
歌詞がほぼ出来上がったらここからは作曲です。僕は基本的に詞が先ですので、書いた歌詞にメロディーをつけていくのですが、とりあえずサビから作るようにしています。昔は頭から作っていたのですが、盛り上がりそうなサビから作った方が逆にAメロBメロが落ち着いた感じになると思うからです。
鼻歌で歌詞に合わせながらメロディーをつけていきます。ここの作業で全てが決まるといっても過言ではないですね。元の部分になるわけですから。
AメロBメロと耳コピ
サビが終わるとAメロBメロを考えます。Aメロは長々とメロディーをつけるよりは、何か短いメロディーの繰り返しでいいと思います。Bメロもしかりです。
で、一通り出来上がったら通して聴いてみます。出来が良い時もあれば悪いところもあります。僕の場合はだいたいそのままで行くのですが、コード進行で面白い部分を作りたい時はあらかじめメロディーをそれに合わせておくこともあります。
ここからは耳コピです。自分の作ったメロディーにコードを付けた時にどんな進行になるか、理論的におかしくないか、逆にワンパターンになってはいないか、などをチェックしていきます。スラスラとはいかない作業ですが、ここも重要な作業です。
記録と記憶
これで大体の曲の流れが出来上がります。ここからがまた大変なのですが、忘れないうちにアコギと歌の録音をなるべく早く行います。譜面が読めない書けないので、記録は録音された音源のみです。なので早めに録音していないとせっかく作ったメロディーが脳内から消えてしまいます。でも安心のは一番最初の作った鼻歌の部分さえ残しておけば、最悪そこまで戻って聞き直せば、まだ思い出すことが出来ます。これもよくあるパターンですね。
テンポを合わせる
次はテンポを合わせた録音をします。なぜテンポを合わせるかといえば、この後録音・打ち込みするドラムやベースのテンポと同じになるからです。それらのテンポを速くしたり遅くしたりする場合、アコギはテンポが合わなくなるので削除扱いになります。なのでテンポの設定は慎重に行います。
カウントから始まってアコギを録音し、次に正式な歌を録音します。ここでは極力はっきりした発音で歌うようにします。
この時点では間奏とかエンディングは決めてないのですが、思いついたままに弾いても差し支えありません。使うのは歌の部分とギターの部分だけです。
ドラムとベース
ギターと歌が正式に録音できたら、ドラムの打ち込みをします。はっきりいってドラムのフレーズはいい加減です。いい加減なのですが大体パターンが決まっているので、そのセオリーに沿った打ち込みをしていきます。この作業の中で、どこでブレイクするか、連続で叩くか、フラムを入れるかなどを決めます。これもこの時点ではいい加減ですが、曲の盛り上がりを想像しながら打ち込みます。
次はベースです。基本的にはバスドラに合わせるのですが、その中でも5度下を入れたり、1オクターブ上げたり下げたりして、変化をつけます。最近は別のトラックにスラップ用のトラックを作って、スラップを入れたりもします。
つたないMIDIキーボード
ここまで出来たらまた次の面倒な作業があります。MIDIシールドを使って、MIDIキーボードとオーディオI/Fを接続します。で、作ったメロティーをドラム・ベース・アコギと合わせて弾きます。が、作ったばかりの曲を流暢に弾く技術などはないわけで、自分が歌っている声とアコギ、ドラム、ベースを合わせて耳コピします。この作業も大変ですね。譜面が読み書きできないというのは不便なものです。耳コピが出来上がったら、MIDI のリアルタイム録音、要はMIDIを使った打ち込みなのですが、なかなか上手に弾けなくても、それはそれでいいのです。ちなみに音源はアルトサックスを使います。他の楽器でもいいのですが、自分にとって聞き取りやすい楽器を選びましょう。
ボカロ、その1
ここからボーカロイド、ボカロを使った作業です。
まず上記で弾いたメロディーをそのままコピペします。その後サックスで弾いたメロディーの音源をミュートすれば、ボカロの声だけが聞こえます。これに歌詞を入れていくわけですが、その前に歌のメロディーに正確に合わせた音の長さ、高さ、強さにする必要があります。基本的には一文字ずつ入力するのですが、歌詞の流し込みといって、連続で音符が続くパートに歌詞を続けて入力できる便利な機能です。ただこれも1文字間違えたら入れ直しになります。地道に作業を続けます。
ボカロ、その2とギター
やがてボカロが完成します。余談ですがボカロは立ち上げた時は「あーあー」と発音してるのですが聞き取りにくいので、僕は「らーらー」に変えるようにしています。
ボカロに間違いがないか、歌詞カードを見ながら何度もチェックします。それが終わると最後にギターのダビングがあります。
アコギは既に録音されてあるのを使ってもいいのですが、ドラムのところで決めた打ち込みに変えないといけないので、そこを決めた上で弾きます。リズムの正確さも求められます。案外難しいです。アコギが終わると次はエレキギターのバッキングです。基本的にはアコギやドラム、ベースとシンクロした演奏になります。むしろここでは音色にこだわった方が、この後良いかと思います。
最後にギターソロを入れます。昔は最初から最後まで同じギターで弾いていましたが、最近はギターソロだけ別で録音するようにしています。ソロのメロディーは決まっている事もありますが、たいていはアドリブです。曲調にあったフレーズを出すように心がけています。
まとめ
と、本当はこの後も動画の編集などの工程があるのですが、ここでは割愛します。曲が出来まして、友人に聞かせたところ大喜びでした。いつもならば「鼻歌」「仮歌と仮アコギ」「ドラム」「ベース」「アコギ」「歌のメロディー」「ボカロ」「エレキギターのバッキング」「ギターソロ」とやることを何日にも分けて行うのですが、今回は憤慨していたこともあり、ぶっ続けで作業を行った結果、2日で完成させました。本来はこれにボカロのハモリとかシンセを入れたりするのですが、メッセージが伝われば、それで良いかと思ってます。
お詫びと反省・・・はしていない
今まで苦労されてきた皆さまには大変ご不便をおかけいたしました。ここに丁重にお詫び申し上げる所存でございます。今後もやっちゃうので、どうかその時はやらせてください。
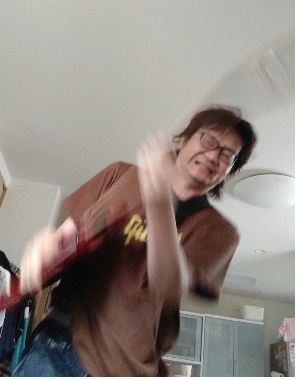


コメント